◯高木公述人
皆さん、こんばんは。ただいま、森戸洋子委員長よりご紹介を賜りました、東町五丁目在住の高木章成と申します。本公聴会の議題であります、前田雄一郎氏提出の23陳情第64号、市議会議員定数の削減を求める陳情書につきまして、慎重審議の上、採択を求める立場から、意見を述べさせていただきます。
まず、初めに、このような公聴会の開催を決断された、森戸委員長以下、議会運営委員の皆様に、市民として心より御礼申し上げます。市民に開かれた小金井市議会の議会改革の歴史に、新たな一歩を残す場に立ち会えておりますことを、とても喜ばしく思っております。今後とも、公聴会制度が活用され、当初予算や決算、市民生活に関わる重要な条例、直接請求等、主要な議題の審査で実施されることを希望いたします。
私は、現在、大学院で行政学・地方自治論を専攻し、LLP議員力検定協会で議員向けの学習教材の開発に携わっております。小金井市におきましては、市民団体として定例会ごとに政策を研究し、陳情書を提出していく活動に取り組んでおります。いずれも、自治体議会と議員の皆さんを応援したいとの思いからです。
1、基本的立場
さて、私はかねてより、小金井市議会は5名でも機能し得ると考えております。ただいま、松井公述人のご発言を拝聴し、松井先生のような方が市議になっていただけたら5名でもよいと、意を強くしたところであります。
以下、事務局に復唱をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
◯齋藤議事係 (代読。重複部分は割愛)
松井公述人からは、民主主義を擁護するため定数は削減してはならない旨のご発言がございましたが、これは、憲法の趣旨には一致しないものと考えます。憲法前文は、「政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し」とし、第1条で国民主権を定めています。地方自治体については、第92条で地方自治の本旨をうたい、これは、団体自治と住民自治からなるとされています。
国民主権や住民自治からして、地域民主主義を擁護し、発展させていくのは市民自身なのです。市民は、選挙したらあとはお任せではなく、選んだ首長と議員たちをしっかりサポートしていかなければならないし、昨年の小金井市政の混乱は、当時の市長とその後援者たちが、この観点を欠き、首都大学の宮台真司教授風に申せば、引き受けて文句を言う民主主義に陥ってしまったがためと考えます。
憲法原理に立ち返れば、民主主義を担うのは国民・市民なのであって、政治家だけが担うものではありません。よって、議員の多寡が民主性のバロメーターになるというような主張には、全く賛同できません。
後に述べますように、議員は市民の民主的意思の判定者であるべきです。ただ、本件陳情書は、議員定数について、コストダウンの観点からしか論じていません。これは極めて不十分です。コストの観点からすれば、議員報酬を含む議会費を検討すべきです。そのためには、議会と議員にどのような役割を期待するかとの点から、最適な議会経費を積算し、市民に示すことから始めるべきです。いたずらに議員定数を削減しても、議会機能が強化・効率化されなければ、身を削ることにはなりません。また、類似市との比較で定数削減をするのも、ほぼ同様に無意味と考えます。
以下、議会機能が強化・効率化のため、議会制度の設計と選挙制度の設計の観点から、本件陳情書に欠ける点を述べてまいりたいと思います。
2、議会制度の設計としての議員定数
現在、国政においては、複数の参議院議員が、生活保護に関する個別の事案について、公然と芸能人の親族を批判し、厚生労働省に調査を求める事態が起きています。また、以前には、年金未納が発覚した芸能人を国会での参考人聴取を、当時の野党第1党の党首が求めたこともありました。これらは、国会や国会議員の役割でしょうか。これは、福祉事務所や社会保険庁の業務であり、国会議員が個別の事案を一々調査・追求していては、膨大な人数の国会議員が必要になってしまいます。
小金井市議会においても、昨今、議員の役割について考えさせられる出来事がありました。ある議員の4月5日付けツイッターによれば、「今日は朝から、議会運営委員会のメンバーと正副議長の力も借りて、2,000人の市民アンケートの袋詰め作業でした。各委員、口もよく動きましたが、手もよく動き、おかげさまで午後3時半に終了しました」とあります。一見、議員が共同作業に取り組んだ微笑ましい場面のように思えますが、私は、これは正副議長や議員の役割なのだろうかと疑問に思いました。本来、袋詰めは議会事務局の業務でしょう。正規職員が行うのが非効率であれば、非常勤職員が行うとか、福祉作業所に委託すれば、それだけ障害者の活動と収入の場を確保することになります。また、市民ボランティアを募る方法も考えられたのではないでしょうか。
もちろん、議員の役割を一般職員の業務のように定型化できないことは理解します。けれども、議事機関としての議会の役割は議決行為であり、議員の役割は表決に純化できます。これに付随する調査や事務作業は議会事務局や外部機関に依頼したり、ご用聞きや市民相談、議会報告活動等の議員活動は政党や政治団体、後援会等が代替することも可能です。ところが、このようなことまで、議員個人が業務として担っているのが実態です。
先ほど、小金井市議は5名でも機能し得ると申しました。実際、教育委員は5名です。最高裁も憲法判断を除けば、5名の小法廷で判断を下しています。5名であっても、合議体としての意思決定は安定的にできるのです。議員が市民の民主的意思の判定者に徹し、それ以外の業務をアウトソーシングしていけば、5名でもよいのではありませんか。ただ、やみくもに5名を主張しているわけではありません。2月24日の本委員会に配付された資料によると、小金井市議会は多摩26市中、本会議開催日数、特別委員会開催日数、請願・陳情件数は1位です。それだけ丁寧な審議をしていただいているわけです。そのためには、外部化できる業務であっても、議員自身が直接、担わなければならないものもあるのかもしれません。そして、それが、5名で担いきれないのであれば、議会として、市民に説明して、定数を5名にプラスアルファをお願いするのが本来であると考えます。
3、選挙制度の設計としての議員定数
さて、政治は選挙制度で決定されると言われることがあります。選挙結果は投票によって決まるのが当然ですが、昨今の国政の選挙制度改革の議論に見られるように、ある結果を期待して選挙制度が設計されることがあります。小金井市議会議員選挙は、いうまでもなく大選挙区単記制です。この制度の場合、無所属候補が比較的参入しやすい割に、結果は比例代表制に近くなるという、議席配分において制度的操作がほぼないのが特性とされています。この大選挙区単記制において、制度として決められるのが、当選者数です。法定得票獲得者が議員定数を超えれば、当選者数は定数と同じになります。逆にいえば、議員定数をいかに定めるかは、いわゆる当選ラインにも影響してくることになります。現行の定数24となった2001年以降、3回の最下位当選者の獲得得票を見ると、1,051票、1,053票、987票です。この得票の有権者比率は、1.217%、1.189%、1.091%となります。参考までに、20位当選者について同様に計算すると、1.278%、1.395%、1.501%となります。当選ラインは、候補者間の得票数の偏りによって前後しますが、小金井市議選では、計量政治学上の絶対当選ライン(投票総数を定数プラス1で割った商)のおおむね65%から70%で推移しています。定数24の場合、有権者の80分の1程度、投票者の42分の1程度の支持が得られれば当選に手が届きます。条例制定や事務監査の直接請求の50分の1、リコールの3分の1、市民参加条例に基づく義務的市民投票の13分の1などに比べて、この比率が妥当なのかも検討が求められます。
おわりに
以上、23陳情第64号に採択を求める立場から、意見を述べさせていただきました。
最後に、本公聴会の公述人が条件付き賛成は私だけで、ほか3名の応募者がすべて反対ということに、極めて残念に思っております。特に、前回の市議選では、定数20を掲げて6名の候補者をお立てになった政党がありましたが、この党の関係者からは応募がなかったと聞いております。ここにも、選挙したらあとはお任せとの風潮があるのかもしれないと思っております。
現在、小金井市議会では、議会改革が進められております。先日は議会報告会が試行され、会場の席が足らないほどの参加者がありました。この延長線上で、議員定数も議論していただきたいと存じます。
前回の市議選で定数削減に慎重な候補者は、あまりそれを公約に打ち出しておられなかったと記憶しております。また、来春に市議選が迫っており、定数条例の改正には一定、半年程度の周知期間が必要であると考えます。
14年前の、市議会議員の定数削減を求める請願書の採択以来、議員定数について、議会意思は明確になっていません。まずは、本陳情書を慎重審議の上、任期中に必ず採決し、採択をいただくことで、各会派・各議員の態度を表明し、改めて議会意思を明らかにしていただくことを強く求め、私の公述を終わります。
最後になりましたが、議会運営委員の皆さん、事務局の皆さんのご高配に感謝を申し上げます。また、傍聴席、ユーストリーム傍聴の皆様、ご清聴ありがとうございました。
◯高木公述人
ご清聴ありがとうございました。
◯松井公述人
日本の投票率の低さというのは、様々な政治の結果としてそうなっているという部分も、私はあると思いますが、やはり、全体として、日本はあまり投票率は高くないんですね。いなかの方なんかへ行って、うんといろいろな圧力があって、90%になってしまうようなところがあって、これはかえっておかしいわけで、ただ、ヨーロッパなんかを見ると、この間、私、ちょうど大統領選挙のときにパリに遊びに行っていたんだけれども、あんなにがちゃがちゃやっても、投票率が80%いくのは当たり前で、今回、1%ちょっと低かったとか言って騒いでいますけれども、日本の衆議院議員選挙、参議院議員選挙で60%台なんていうのは、ちょっと、ヨーロッパでは信じられないですよね。もっとも、オランダみたいに、投票に行かないと罰金を取るという国もあるけれども、それはやり過ぎだと私は思っているんだけれども、ただ、全体として、やはり、国民と議員活動、あるいは行政の首長も含めて、政治との距離が、ちょっと、先ほどの公述人からもありましたけれども、どうもうまくいっていない。例えば、アメリカ人であれば、そこらの主婦が、何か文句があると、大統領に手紙を出して、大統領だってろくに読んでいないと思うけれども、そういう担当者がいて、ちゃんと手紙をくれるんです。そういうつながり方が、ちょっと弱いのかなという気もしますね。
◯高木公述人
ご質問ありがとうございます。投票率の低下の問題ですが、原因は幾つかあるのかなと思います。一つは、政治そのものへの無関心、どうでもいいやというもの、もう一つは、政治には関心があるけれども、関わりたくないという政治に対する拒否感、もう一つは、先ほども述べた、大選挙区単記制の問題ですが、いろいろな議員さんにお世話になっているから、誰に入れようか困ってしまうという、三つぐらいに分かれるのかなと思います。
◯高木公述人
第1点目の、どうでもいいやということについては、選択肢がきちんと判断できる候補者となれば、投票に行く期待が高まると思われます。第2点の政治への拒否感は、市議選の争点が明確なら、個々の議員の議決責任が分かりやすくなることで呼び戻せると思います。3点目については、ケースバイケースではありますが、お世話になっている議員が減れば、選択の苦労も減ると思われます。
◯宮崎委員
本日は、お忙しいところ、公述をありがとうございます。
私から質問したいのは、まず、先ほど松井さんがおっしゃったように、大変に首長の力というのは強いんですね。それに対抗していくというのが、二元代表制の中の市議会であると思っておりまして、その観点から、今、議会基本条例を制定しようと、議会運営委員会は頑張っているわけです。その観点から、皆様にお伺いしたいと思うんですね。
今回は、削減に賛成の方がお一人、反対の方が3人ということなんですけれども、それぞれの観点から見て、この議会の、行政に対する権能をしっかりと果たしていくというためには、どのようなことが必要と考えられるでしょうか。これが、今回の議員定数削減ということに結び付けて、それぞれのお考えをお聞かせください。
◯高木公述人
ご質問ありがとうございます。私も、問題意識としては、小金井市議会の議員の皆さんは、本当に頑張っているなと思うんです。ただ、議員が頑張り過ぎて、議員が市民を支えるという場面が多くなっているのではないかという問題意識も同時に持っております。
◯高木公述人
もっと議員が、議会がやっていることを市民に渡していくことが大切だと思います。例えば、このような公聴会制度もそうですし、議員の調査活動を、NPOに委託しているような事例も、ほかの自治体では見られます。また、自治法第100条第2項を使って、専門家を議会に入ってもらうようなことも、議会のパワーアップにはなるのではないでしょうか。
◯渡辺(大)委員
公述人の皆様、今日は、お忙しい中、ありがとうございます。
今日は、実はいろいろなことをお伺いしたいんですが、時間も限られておりますので、今日の主題が議員定数ということになっておりますので、あまり、私の自説は述べないで、4人の方から、ずばり数字でご意見を頂ければと思っております。
現状、小金井市は議員定数24名ということになっております。これは、小金井市がまだ町だったころに、26名でスタートいたしまして、その後、しばらく26名のままだったんですが、私がちょうど議員になった1期目は、ですので、26の選挙でした。2期目のときに、25になりまして、3期目の選挙のときに、24ということで、二元になって、現在まで、24でしばらく推移しておりますが、ずばり伺いたいのは、現状、24の定数に関しまして、皆さん、それぞれ、るるご意見を述べられておりましたが、そのようなお考えからして、この定数を、増やすとしたら、例えば、幾つまで増やしたらいいと考えていらっしゃるのか、あるいは、現状維持でいいとなれば、現状維持。また、減らすべきだとしたら、幾つまで減らすべきだと、それぞれお考えになっているのか、はっきりとした数字で言えれば、その数字で。もし、漠然としていれば、この程度ということでも結構なんですが、その具体的な数字ということで、ご意見を頂ければありがたいと思います。
◯高木公述人
ご質問ありがとうございます。結論から申し上げると、5プラスアルファで、プラスアルファの部分は、なぜ必要かということを、議会に説明責任を課すべきだというのが結論です。
◯高木公述人
今般、政権交代後の地方自治法の改正で、議員の上限数が撤廃されました。要するに、各自治体がゼロベースで考えなさいというのが、国会答弁で出ています。よって、ゼロベースで考えるということは、何人必要かという説明責任を、今までは、法律で決まっているからとか、今までやってきたからとかいう説明になるわけですが、これからは、それは許されないというのが、今回の自治法改正の趣旨と受け止めるべきではないでしょうか。
◯宮下委員
高木章成さんに質問したいと思います。二元代表制と言われている中で、市長は独任制、1人で、自分で判断するという、こういう立場です。議員の方は合議制という形で、多様な意見を反映するという、このように役割が分かれていると思うんですね。そういう関係で、現状よりも減らして、持論でいかれると5名ということですが、多様な民意を反映させるために、という観点からすると、ちょっと、5名だと厳しいのかなと思うんですが、その点はどうでしょうか。
◯高木公述人
ご質問ありがとうございます。自治体の二元代表制の教科書的な説明として、首長は民意の集約を担い、議会は民意の反映を担うという説明がされます。ただ、私は、本当にその説明が正しいのかなと思っております。なぜかと申しますと、議会においても、最後は多数決で決定されるわけです。そこでは何らかの集約が行われているわけです。ですから、民意の反映、すなわち、議論の場では、議会というものの中に誰でも入ってきてもらって、議論を行って、それを受けて、議員が、何が民意かを判定する上では、5名で十分ではないかという問題提起をさせていただきました。
◯森戸委員長
ありがとうございます。
最後に、私の方から伺わせていただきます。議会には、三つの機能があることが、地方自治法ではうたわれています。一つは、先ほど来出ておりますが、首長、市長の市政運営を監視する機能。二つ目には、市民の代表機構として、市民の要望、声を政策立案し、条例を提案する機能。そして、三つ目には、市長から提案をされる議案党について議決するという機能がうたわれているわけです。
皆さんから見て、この三つの機能と定数削減について、どのようにお考えになっているかということについて伺いたいと思います。
◯高木公述人
ご質問ありがとうございます。三つの機能の問題は、本当は、反問権が欲しいぐらいの問題ですが、お答えさせていただきます。
一つ目の監視と、二つ目の参加の機能ですか、別に、議会でなくてもできる部分が大きいだろうと思います。ただ、三つ目の議決機能は、憲法第93条と自治法第96条で、議会しかできないものとされています。要するに、議決というのは、首長提案が正しいのかどうかをアンパイヤしているわけです。
ところが、今の自治体議会は、アンパイヤをやりながら、首長の応援も反対も一手に引き受けているわけです。実態はこうですが、議会というアリーナの中で、首長以外にも、参加したい市民がみんなアリーナの中で話し合ってもらって、その上で、議員が判断するという方向にどうしてもいかなければ、民意の反映はされない議会になるのではないかという危機感を持っております。
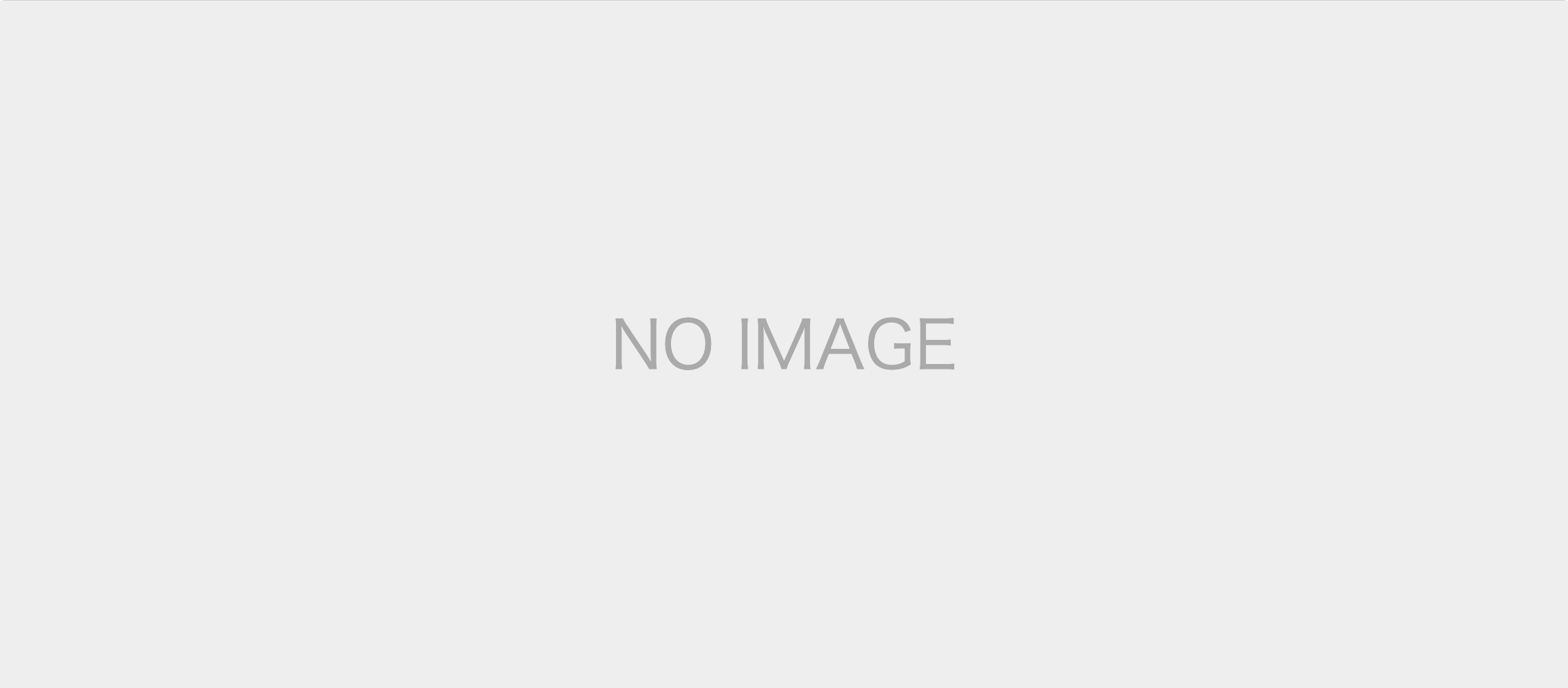

コメント